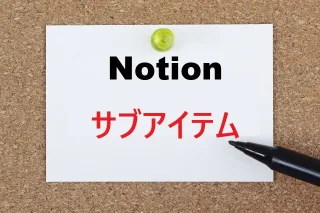 雑学
雑学 Notionサブアイテムの作り方と活用法を完全解説!効率化のための実践テクニック
Notionを使っていて「このタスクの下にもっと細かい作業項目を作りたい」「プロジェクトの中で個別の要素を管理したい」と思ったことはありませんか?そんな時に便利なのが「サブアイテム」という概念です。しかし、いざサブアイテムを作ろうと思っても...
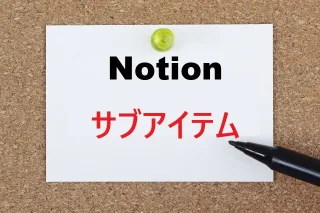 雑学
雑学 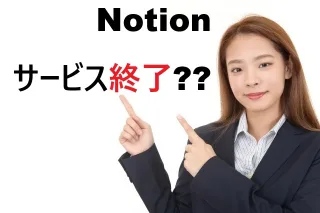 雑学
雑学 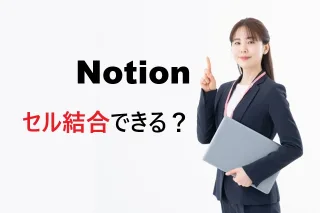 雑学
雑学 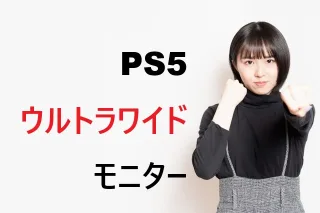 雑学
雑学  雑学
雑学 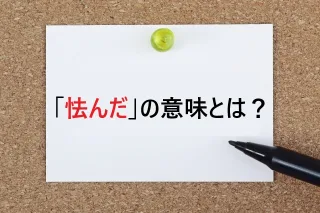 雑学
雑学 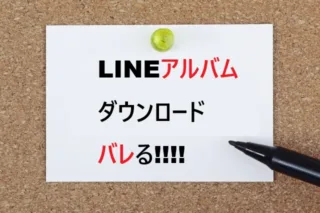 雑学
雑学 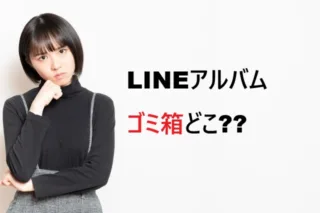 雑学
雑学 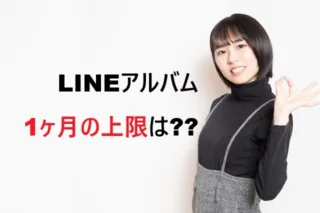 雑学
雑学  雑学
雑学