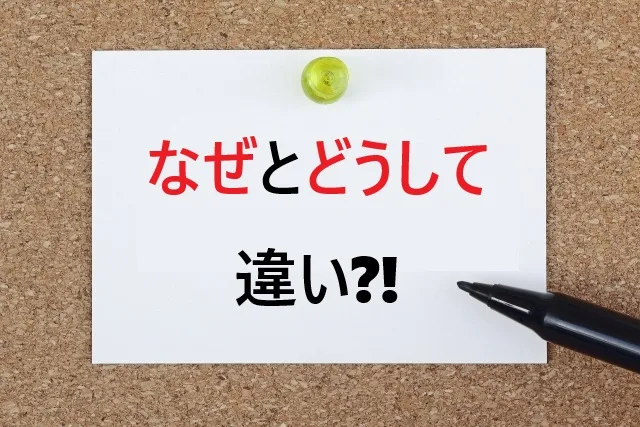「なぜそうなったの?」「どうしてそうなったの?」——日常会話でもビジネスシーンでも、理由を尋ねるときに私たちは何気なくこれらの言葉を使っています。しかし、いざ「この場面ではどちらが正しいのだろう?」と考え始めると、意外と明確な答えが見つからないものです。
特にビジネスメールを書くときや、目上の人と話すとき、あるいは日本語を学習している方にとっては、この使い分けは切実な問題かもしれません。「なぜ」を使うべきところで「どうして」を使ってしまって、少しカジュアルすぎる印象を与えてしまった……そんな経験はありませんか?
実は、この2つの疑問詞には明確な違いがあります。そして、その違いを理解することで、相手に与える印象をコントロールし、より適切なコミュニケーションができるようになります。
この記事では、「なぜ」と「どうして」の基本的な違いから、フォーマル度の違い、ニュアンスの違い、そして実際のシーン別使い分けまで、徹底的に解説します。さらに、「なんで」も含めた3つの疑問詞の比較や、よくある間違い、英語の「why」との対応関係まで網羅しています。
この記事を読み終える頃には、あなたは自信を持って「なぜ」と「どうして」を使い分けられるようになっているはずです。それでは、早速見ていきましょう。
この記事で分かること:
- 「なぜ」と「どうして」の基本的な違いと定義
- フォーマル度とニュアンスの違い
- ビジネス・日常・文章での具体的な使い分け方
- 「なんで」も含めた3つの疑問詞の使い分け
- よくある間違いと注意点
- 英語の「why」との対応関係
「なぜ」と「どうして」の基本的な違い
辞書での定義
まず、国語辞典ではこれらの言葉がどのように定義されているか見てみましょう。
「なぜ」の定義:
- 理由や原因を尋ねる疑問詞
- 「何故」という漢字表記もある
- 論理的な因果関係を問う際に使用される
「どうして」の定義:
- 理由や原因、方法を尋ねる疑問詞
- 「如何して」という漢字表記もある
- やや感情的・共感的なニュアンスを含む
この時点では、両者ともに「理由や原因を尋ねる」という点で共通しており、基本的な機能は同じであることが分かります。
基本的な意味の共通点
「なぜ」と「どうして」は、どちらも以下のような共通点を持っています:
共通する使用目的:
- 理由の質問:何かが起こった理由を尋ねる
- 原因の追求:ある結果に至った原因を知りたい
- 説明の要求:相手に説明を求める
例えば、以下の文ではどちらを使っても意味は通じます:
- 「なぜ遅刻したのですか?」
- 「どうして遅刻したのですか?」
どちらも遅刻の理由を尋ねている点では同じです。では、何が違うのでしょうか?
決定的な違いとは
実は、「なぜ」と「どうして」の決定的な違いは、フォーマル度とニュアンスにあります。
主な違い:
- フォーマル度:「なぜ」の方がフォーマル、「どうして」はややカジュアル
- 論理性:「なぜ」は論理的・客観的、「どうして」は感情的・主観的
- 距離感:「なぜ」は距離を保つ、「どうして」は親近感を生む
- 使用場面:「なぜ」はビジネスや論文、「どうして」は日常会話
この違いを理解することが、適切な使い分けの第一歩となります。次のセクションでは、このフォーマル度の違いについてさらに詳しく見ていきましょう。
フォーマル度で見る「なぜ」と「どうして」
「なぜ」が適した場面
「なぜ」は、以下のような場面で特に適しています:
1. ビジネス文書・メール
例:なぜこのプロジェクトが遅延しているのか、ご説明いただけますでしょうか。
ビジネスメールや報告書では、「なぜ」を使うことで専門的で論理的な印象を与えることができます。
2. 学術論文・レポート
例:なぜこの仮説が成立するのか、以下で検証する。
論文やレポートでは、客観的な分析が求められるため、「なぜ」が最適です。
3. フォーマルなプレゼンテーション
例:なぜ当社の製品が選ばれるのか、3つの理由をご説明します。
プレゼンテーションで論理的な説明をする際には、「なぜ」を使うことで説得力が増します。
4. 目上の人への質問(特にビジネス)
例:なぜそのようにお考えになったのか、お聞かせいただけますか。
目上の人に理由を尋ねる際、「なぜ」を使うことで適切な敬意を示せます。
「どうして」が適した場面
一方、「どうして」は以下のような場面で適しています:
1. 日常会話
例:どうして今日は早く帰ってきたの?
友人や家族との会話では、「どうして」の方が自然で親しみやすい印象を与えます。
2. 子供への質問
例:どうして宿題をやらなかったの?
子供に対しては、「どうして」の方が優しく、責めるような印象を与えにくくなります。
3. 共感を示したい場面
例:どうしてそんなに悲しそうなの?大丈夫?
相手の感情に寄り添いたいとき、「どうして」を使うことで温かみが伝わります。
4. カジュアルな職場環境
例:どうしてそのアイデアを思いついたの?面白いね!
同僚や部下との気軽な会話では、「どうして」の方が親近感を生みます。
フォーマル度の違いが生まれた背景
では、なぜこのようなフォーマル度の違いが生まれたのでしょうか?
歴史的・言語学的背景:
「なぜ」は、「何故(なにゆえ)」が変化した言葉で、古くから文語的な表現として使われてきました。漢字で「何故」と書くことからも分かるように、書き言葉としての性格が強い言葉です。
一方、「どうして」は「どう(如何)」+「して」という構造で、より口語的な成り立ちを持っています。「どのようにして」という意味合いも含むため、プロセスや方法への関心も含まれています。
この成り立ちの違いが、現代における使い分けの基礎となっているのです。
ニュアンスの違いを徹底比較
フォーマル度の違いに加えて、「なぜ」と「どうして」にはニュアンスの違いもあります。このニュアンスの違いを理解することで、より繊細なコミュニケーションが可能になります。
論理的追求の「なぜ」
「なぜ」は、論理的な因果関係を追求する際に使われます。
特徴:
- 客観性:感情を排除した客観的な質問
- 分析的:原因を論理的に分析しようとする姿勢
- 距離感:相手との適度な距離を保つ
具体例:
ビジネス:なぜ売上が減少したのか、データを分析しましょう。
→ 客観的な分析が目的
学術:なぜこの現象が起こるのか、科学的に解明する必要がある。
→ 論理的な追求が目的
「なぜ」を使うことで、「感情ではなく論理で考えている」という印象を与えることができます。
感情的共感の「どうして」
一方、「どうして」は、相手の感情に寄り添う際に適しています。
特徴:
- 主観性:話し手の感情や関心が含まれる
- 共感的:相手の気持ちを理解しようとする姿勢
- 親近感:相手との心理的距離を縮める
具体例:
共感:どうしてそんなに頑張ったの?すごいね!
→ 感情的な共感が含まれる
心配:どうして連絡くれなかったの?心配したよ。
→ 相手への関心と感情が含まれる
「どうして」を使うことで、「あなたのことを気にかけている」という温かみを伝えることができます。
相手への印象の違い
同じ内容でも、「なぜ」と「どうして」では相手が受ける印象が大きく変わります。
比較例1:遅刻を問う場面
- 「なぜ遅刻したのですか?」→ 責任追及のニュアンスが強い
- 「どうして遅刻したのですか?」→ 事情を聞こうとする柔らかいニュアンス
比較例2:意見を求める場面
- 「なぜそう思うのですか?」→ 論理的根拠を求める
- 「どうしてそう思うのですか?」→ 気持ちや考えを聞きたい
比較例3:行動の理由を尋ねる場面
- 「なぜそのような行動を取ったのですか?」→ 冷静な分析
- 「どうしてそんなことをしたの?」→ 感情的な関与
このように、同じ「理由を尋ねる」行為でも、相手への印象は大きく異なります。状況に応じて適切に使い分けることが、円滑なコミュニケーションの鍵となります。
シーン別の使い分け実践ガイド
理論は理解できても、実際の場面でどう使い分けるかが重要です。ここでは、具体的なシーン別に最適な使い分けを見ていきましょう。
ビジネスシーンでの使い分け
ビジネスシーンでは、相手との関係性と状況によって使い分けます。
1. 上司・取引先への質問
推奨:「なぜこの方針を選択されたのか、ご教示いただけますでしょうか。」
避ける:「どうしてこの方針にしたんですか?」
→ フォーマルな場面では「なぜ」を使用
2. 同僚への気軽な質問
OK:「どうしてその方法を選んだの?」
OK:「なぜその方法を選んだの?」
→ どちらでも可。親近感を出すなら「どうして」
3. 部下への質問(指導的)
推奨:「なぜこのようなミスが発生したのか、原因を分析してください。」
配慮:「どうしてこういうことになったの?一緒に考えよう。」
→ 「なぜ」は論理的分析、「どうして」は共に考える姿勢
4. メールでの問い合わせ
ビジネスメール:「なぜ納期が遅延しているのか、ご説明いただけますでしょうか。」
社内メール(親しい):「どうして今日は早く帰れたの?」
→ 外部とのメールは基本的に「なぜ」
5. プレゼンテーション
推奨:「なぜ当社の製品を選ぶべきなのか、3つの理由をお伝えします。」
→ プレゼンでは論理性を重視し「なぜ」を使用
日常会話での使い分け
日常会話では、相手との関係性と感情の度合いで使い分けます。
1. 家族との会話
自然:「どうして今日は遅くなったの?」
やや硬い:「なぜ遅くなったの?」
→ 家族には「どうして」が自然
2. 友人との会話
カジュアル:「どうしてそれ買ったの?」「なんでそれ買ったの?」
やや改まった:「なぜそれを選んだの?」
→ 友人間では「どうして」「なんで」が一般的
3. 子供への質問
優しい:「どうして泣いているの?」
やや厳しい:「なぜ約束を守らなかったの?」
→ 共感するときは「どうして」、教育的には「なぜ」
4. 初対面の人との会話
丁寧:「なぜこの仕事を選ばれたのですか?」
フレンドリー:「どうしてこの仕事を選んだんですか?」
→ 距離感によって使い分け
5. 感情を伴う場面
共感:「どうしてそんなに頑張ったの?すごいね!」
客観的:「なぜそこまで頑張れたの?」
→ 感情を込めるなら「どうして」
文章・メールでの使い分け
書き言葉では、文章の種類と目的によって使い分けます。
1. ビジネス文書
報告書:「なぜこのような結果となったのか、以下に分析する。」
議事録:「なぜこの提案が採用されたのか、理由は3つある。」
→ ビジネス文書では「なぜ」が基本
2. 学術論文・レポート
論文:「なぜこの仮説が成立するのか、実験により検証した。」
レポート:「なぜこの問題が発生したのか、考察する。」
→ 学術的な文章では「なぜ」一択
3. ブログ・SNS
フォーマル:「なぜこの商品がおすすめなのか、理由を説明します。」
カジュアル:「どうしてこれを買ったのか、理由を話します!」
→ 読者層とトーンによって使い分け
4. 小説・エッセイ
描写:「彼女はどうしてそんなに悲しそうなのだろう。」
分析:「なぜ彼がそのような行動を取ったのか、理解できなかった。」
→ 感情描写は「どうして」、分析は「なぜ」
5. 手紙・メッセージ
親しい相手:「どうして連絡くれなかったの?」
フォーマル:「なぜご連絡いただけなかったのでしょうか。」
→ 相手との関係性で使い分け
「なんで」も含めた3つの疑問詞の違い
実は、理由を尋ねる疑問詞には「なぜ」「どうして」の他に「なんで」もあります。この3つを比較することで、より的確な使い分けができるようになります。
「なんで」の特徴とカジュアル度
「なんで」は、3つの中で最もカジュアルな疑問詞です。
「なんで」の特徴:
- 最もカジュアル:友人や家族との会話に最適
- 口語的:話し言葉で使用され、書き言葉では通常使わない
- 感情的:驚きや不満などの感情を含みやすい
- 親近感:相手との距離が近いことを前提とする
使用例:
友人:「なんで昨日来なかったの?」
家族:「なんでそんなに遅いの?」
子供:「なんで宿題しなきゃいけないの?」
注意点:
- ビジネスシーンでは基本的に使わない
- 目上の人には使用しない
- 書き言葉では避ける
- 場合によっては失礼な印象を与える
3つの疑問詞の使い分けマトリックス
それでは、3つの疑問詞を比較してみましょう。
フォーマル度の順位:
最もフォーマル → 「なぜ」
中間 → 「どうして」
最もカジュアル → 「なんで」
使用場面の比較:
| 場面 | なぜ | どうして | なんで |
|---|---|---|---|
| ビジネス文書 | ◎ | △ | × |
| ビジネスメール | ◎ | △ | × |
| 論文・レポート | ◎ | × | × |
| プレゼン | ◎ | △ | × |
| 目上への質問 | ◎ | ○ | × |
| 同僚との会話 | ○ | ◎ | ○ |
| 友人との会話 | △ | ◎ | ◎ |
| 家族との会話 | △ | ◎ | ◎ |
| SNS・ブログ | ○ | ◎ | ○ |
| 小説・エッセイ | ○ | ◎ | ○ |
ニュアンスの比較:
- なぜ:論理的、客観的、分析的
- どうして:共感的、主観的、親しみやすい
- なんで:感情的、驚き、不満
場面に応じた最適な選択
具体的な場面で、どの疑問詞を選ぶべきか見てみましょう。
場面1:取引先への問い合わせメール
最適:「なぜ納期が変更になったのか、ご説明いただけますでしょうか。」
NG:「どうして納期が変更になったんですか?」
絶対NG:「なんで納期が変わったんですか?」
場面2:親しい同僚との雑談
自然:「なんで昨日休んだの?」「どうして昨日休んだの?」
やや硬い:「なぜ昨日休んだの?」
場面3:子供への質問
優しい:「どうして泣いているの?」「なんで泣いているの?」
教育的:「なぜ約束を守らなかったのか、説明しなさい。」
場面4:ブログ記事のタイトル
フォーマル:「なぜこの方法が効果的なのか」
親しみやすい:「どうしてこの方法がおすすめなの?」
超カジュアル:「なんでこれがいいの?」
選択の基準:
- 相手との関係性:距離が近いほどカジュアルに
- 場の雰囲気:フォーマルな場では「なぜ」
- 伝えたい印象:論理性なら「なぜ」、共感なら「どうして」
- 媒体:書き言葉は「なぜ」、話し言葉は「どうして」「なんで」
よくある間違いと注意点
使い分けを理解しても、実際には間違いやすいポイントがあります。ここでは、よくある間違いと注意点を見ていきましょう。
ビジネスメールでのNG例
ビジネスメールでは、以下のような間違いが見られます。
NG例1:カジュアルすぎる表現
NG:「なんで返信くれないんですか?」
OK:「なぜご返信いただけないのでしょうか。」
NG例2:感情的な表現
NG:「どうしてこんなミスをしたんですか?」
OK:「なぜこのようなミスが発生したのか、ご説明ください。」
NG例3:親しすぎる表現
NG:「どうして会議欠席したの?」
OK:「なぜ会議を欠席されたのか、理由をお聞かせください。」
正しい表現のコツ:
- 基本的に「なぜ」を使用
- 丁寧語・尊敬語と組み合わせる
- 感情を排除した客観的な表現を心がける
目上の人への質問での注意点
目上の人に理由を尋ねる際は、特に注意が必要です。
注意点1:詰問のような印象を避ける
NG:「なぜそうされたんですか?」(詰問調)
OK:「なぜそのようにお考えになったのか、お聞かせいただけますでしょうか。」
注意点2:クッション言葉を使う
基本:「恐れ入りますが、なぜ〜」
丁寧:「差し支えなければ、なぜ〜」
最大級:「失礼ですが、なぜ〜をお聞かせいただけますでしょうか。」
注意点3:「どうして」は避ける
やや失礼:「どうしてそう思われるんですか?」
適切:「なぜそのようにお考えなのか、ご教示いただけますか。」
推奨フレーズ:
- 「なぜ〜なのか、ご説明いただけますでしょうか。」
- 「なぜ〜とお考えなのか、お聞かせください。」
- 「なぜ〜なのか、ご教示いただけますと幸いです。」
日本語学習者が陥りやすい誤用
日本語学習者の方は、以下のような間違いに注意しましょう。
誤用1:全て「なぜ」で統一
不自然:「なぜあなたは悲しいの?」(友人への質問)
自然:「どうして悲しいの?」
→ 場面に応じた使い分けが必要
誤用2:論文で「どうして」を使う
NG:「どうしてこの現象が起こるのか、研究した。」
OK:「なぜこの現象が起こるのか、研究した。」
→ 学術的な文章では「なぜ」
誤用3:ビジネスで「なんで」を使う
絶対NG:「なんでこの企画が通らなかったんですか?」
OK:「なぜこの企画が通らなかったのでしょうか。」
→ ビジネスでは「なんで」は使わない
学習のコツ:
- まずフォーマルな「なぜ」をマスター
- 慣れてきたら「どうして」を使い始める
- 「なんで」は親しい人との会話のみ
英語の「why」との対応関係
英語を学習している方や、英語から日本語に翻訳する際に役立つ情報です。
whyの翻訳パターン
英語の「why」は、文脈によって異なる日本語に翻訳されます。
フォーマルな文脈
Why did this happen? → なぜこのようなことが起こったのか。
Why is this important? → なぜこれが重要なのか。
カジュアルな文脈
Why are you crying? → どうして泣いているの?
Why didn't you come? → どうして来なかったの?
感情的な文脈
Why are you so late? → なんでそんなに遅いの?
Why did you do that? → なんでそんなことしたの?
英語から日本語への変換のコツ
英語の「why」を日本語にする際のコツを見ていきましょう。
コツ1:文体を見る
学術論文のwhy → 「なぜ」
ビジネス文書のwhy → 「なぜ」
日常会話のwhy → 「どうして」「なんで」
コツ2:感情の有無を判断
感情なし:Why is the sky blue? → なぜ空は青いのか。
感情あり:Why are you so happy? → どうしてそんなに嬉しそうなの?
コツ3:相手との関係性を考慮
上司:Why did you choose this? → なぜこれを選んだのですか。
友人:Why did you choose this? → どうしてこれを選んだの?
日本語独自のニュアンス
実は、日本語の「なぜ」「どうして」「なんで」の使い分けは、英語にはない独自の特徴です。
日本語の特徴:
- 敬語との組み合わせ:「なぜ」+丁寧語で最大の敬意
- 距離感の調整:疑問詞だけで親疎を表現できる
- 感情の込め方:疑問詞の選択で感情のニュアンスが変わる
英語話者への説明例:
"Why"は日本語では場面によって使い分けます:
- フォーマル・論理的 → なぜ
- 日常的・共感的 → どうして
- 超カジュアル・感情的 → なんで
この使い分けをマスターすることで、より自然で適切な日本語表現ができるようになります。
よくある質問(FAQ)
ここでは、「なぜ」と「どうして」の使い分けについて、よく寄せられる質問にお答えします。
Q1. 「なぜ」と「どうして」はどちらが丁寧ですか?
A. 一概には言えませんが、「なぜ」の方がフォーマルで、ビジネスや公的な場面では丁寧な印象を与えます。
ただし、丁寧さは疑問詞だけで決まるわけではありません。重要なのは、疑問詞と敬語表現の組み合わせです。
より丁寧:「なぜそのようにお考えになったのか、ご教示いただけますでしょうか。」
やや丁寧:「どうしてそう思われるのですか?」
ビジネスシーンや目上の人への質問では、「なぜ」+丁寧な敬語表現を使うことをおすすめします。
Q2. 論文やレポートではどちらを使うべき?
A. 論文やレポートでは、「なぜ」を使うべきです。
学術的な文章では、客観的で論理的な表現が求められます。「どうして」は口語的で主観的なニュアンスがあるため、論文やレポートには適していません。
論文での正しい表現:
「なぜこの仮説が成立するのか、以下で検証する。」
「なぜこの結果が得られたのか、考察する。」
論文で避けるべき表現:
「どうしてこの仮説が成立するのか〜」(口語的すぎる)
「なんでこの結果になったのか〜」(絶対NG)
ただし、小説やエッセイなど、感情や主観を表現する文章では「どうして」も使用できます。
Q3. 子供に対してはどちらを使う方が良い?
A. **共感するときは「どうして」、教育的に論理を教えるときは「なぜ」**を使い分けるのが効果的です。
子供の感情に寄り添いたいとき:
「どうして泣いているの?どうしたの?」
「どうしてそんなに嬉しそうなの?」
→ 「どうして」は優しく、親しみやすい印象
子供に論理的思考を教えたいとき:
「なぜそうなったのか、考えてみようか。」
「なぜ約束を守らなかったのか、説明してください。」
→ 「なぜ」は論理性を重視し、やや厳格な印象
年齢が上がるにつれて、「なぜ」を使う機会を増やすことで、論理的思考力を育てることができます。
Q4. 「何故」「如何して」の漢字表記は使うべき?
A. 現代では、ひらがな表記(「なぜ」「どうして」)が一般的で推奨されます。
漢字表記は古風で硬い印象を与えるため、以下のような場合を除いて、通常はひらがなで書きます。
漢字を使う場面:
- 古文や漢文の引用
- 歴史的な文書を再現する場合
- 特別な文学的効果を狙う場合
現代の一般的な使い方:
推奨:「なぜこのような結果になったのか。」
古風:「何故このような結果になったのか。」
推奨:「どうしてそう思ったの?」
古風:「如何してそう思ったの?」
特にビジネス文書や論文では、ひらがな表記が標準です。
Q5. ビジネスメールで理由を尋ねる最適な表現は?
A. ビジネスメールでは、「なぜ」+丁寧な敬語表現+クッション言葉の組み合わせが最適です。
推奨表現パターン:
パターン1:基本形
「なぜ〜なのか、ご説明いただけますでしょうか。」
「なぜ〜となったのか、お聞かせいただけますか。」
パターン2:クッション言葉付き
「恐れ入りますが、なぜ〜なのか、ご教示いただけますでしょうか。」
「差し支えなければ、なぜ〜となったのか、お教えいただけますか。」
パターン3:より丁寧
「誠に恐縮ですが、なぜ〜なのか、ご説明いただけますと幸いです。」
避けるべき表現:
NG:「どうして〜なんですか?」(カジュアルすぎる)
NG:「なんで〜なんですか?」(失礼)
NG:「なぜですか?」(唐突で威圧的)
相手との関係性や状況に応じて、適切な丁寧さのレベルを選びましょう。
まとめ:「なぜ」と「どうして」を使い分けるポイント
ここまで、「なぜ」と「どうして」の違いについて詳しく見てきました。最後に、重要なポイントをまとめます。
基本的な違いのおさらい
「なぜ」の特徴:
- フォーマルで論理的
- ビジネス、学術、公的な場面に適している
- 客観的な分析や原因追求に使用
- 相手との適度な距離を保つ
「どうして」の特徴:
- カジュアルで共感的
- 日常会話、親しい関係に適している
- 感情や主観を含む質問に使用
- 相手との心理的距離を縮める
「なんで」の特徴:
- 最もカジュアルで口語的
- 友人や家族との会話に限定
- 感情的なニュアンスを含みやすい
- ビジネスや公的な場面では使用しない
シーン別使い分けの簡単な覚え方
使い分けに迷ったら、以下の基準で判断してください:
1. フォーマル度で判断
フォーマル → 「なぜ」
中間 → 「どうして」
カジュアル → 「なんで」
2. 相手との関係で判断
目上・取引先 → 「なぜ」
同僚 → 「なぜ」「どうして」
友人・家族 → 「どうして」「なんで」
3. 媒体で判断
ビジネス文書・論文 → 「なぜ」
メール(ビジネス) → 「なぜ」
メール(親しい人) → 「どうして」
会話 → 「どうして」「なんで」
4. 目的で判断
論理的分析 → 「なぜ」
共感・心配 → 「どうして」
気軽な質問 → 「なんで」
今日から実践できること
この記事で学んだことを、今日から実践してみましょう:
ステップ1:ビジネスメールをチェック
- 送信前に「なぜ」「どうして」「なんで」の使い方を確認
- フォーマルな場面では「なぜ」を使っているか確認
ステップ2:会話で意識する
- 目上の人には「なぜ」+丁寧な表現
- 友人や家族には「どうして」「なんで」でOK
ステップ3:文章を書くときに注意
- 論文・レポートは「なぜ」のみ
- ブログやSNSは読者層に合わせて選択
ステップ4:間違いを恐れない
- 使い分けは慣れが重要
- 迷ったら「なぜ」を使えば無難
最後に
「なぜ」と「どうして」の使い分けは、日本語の微妙なニュアンスを表現する重要なスキルです。この記事で紹介した基準を参考に、状況に応じて適切に使い分けることで、より円滑で効果的なコミュニケーションができるようになります。
最初は意識的に使い分ける必要がありますが、慣れてくれば自然に適切な表現を選べるようになります。ビジネスシーンでもプライベートでも、この使い分けをマスターすることで、相手に与える印象をコントロールし、より良い人間関係を築くことができるでしょう。
あなたも今日から、「なぜ」と「どうして」を意識的に使い分けてみませんか?きっと、コミュニケーションの質が向上することを実感できるはずです。