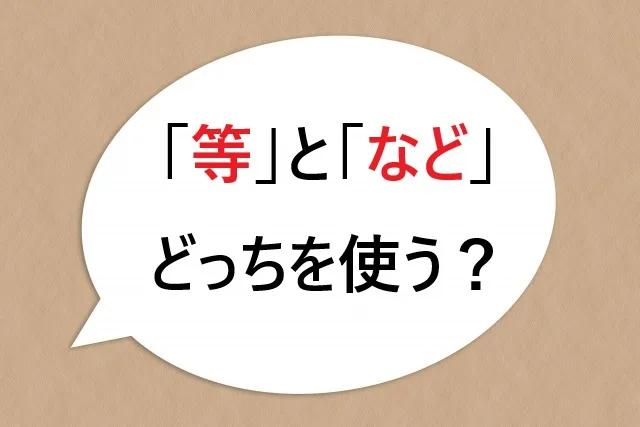公用文を作成する際に「条件等を満たす場合」と書くべきか、「条件などを満たす場合」と書くべきか迷ったことはありませんか?
官公庁や自治体で働く職員、行政書士、企業の行政対応担当者にとって、公用文での「等」「など」の使い分けは重要なスキルです。適切でない使い方をすると、文書の統一性や読みやすさに影響する可能性があります。
この記事では、公用文における「等」「など」の一般的な使い分け方法を、文化庁の公用文作成指針や各省庁のマニュアルを参考に解説します。法令・条例での使用例、よくある事例とその改善案も紹介し、実務での参考情報を提供します。
重要な注意事項 本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的アドバイスや公式な指導ではありません。実際の公用文作成においては、所属する機関の規定や最新の指針を必ず確認してください。具体的な判断については、法務担当者や上司にご相談することをお勧めします。
公用文とは?「等」「など」使い分けの一般的な考え方
公用文での「等」「など」使い分けを理解するには、まず公用文の特性と、「等」が多く使われる背景を把握することが参考になります。
公用文の定義と特徴
公用文とは、国や地方自治体などの公的機関が作成する文書の総称です。法令、条例、通達、申請書、報告書、議事録など、行政業務で使用される文書が該当します。
公用文には一般的に以下の3つの基本原則があるとされています:
正確性: 誤解を招きにくい明確な表現 明確性: 多くの人が同じ理解ができる表現 簡潔性: 無駄な表現を避けた効率的な文章
これらの原則を満たすため、公用文では統一された表記ルールが重視される傾向があります。
公用文で「等」がよく使われる背景
公用文で「等」が多く使用される背景には、以下のような理由があると考えられます:
格式性の維持: 漢字表記により文書の格式を保つ 客観性の確保: 感情的なニュアンスを避けた表現 文字数の効率化: 漢字一文字で表現でき、文書の簡潔性に貢献 慣例的な使用: 従来からの公用文での標準的な表記
文化庁の「公用文作成の要領」(※)でも、例示表現として「等」の使用について言及されています。
※参考資料:文化庁「公用文作成の要領」
「など」が使われる場合の考え方
公用文でも「など」が使用される場合があります:
住民向け広報文書: 一般市民の理解しやすさを重視する場合 説明資料: 専門用語の説明や補足説明において 親しみやすさを重視: 読み手との距離感を考慮する場合
ただし、これらの場合でも文書全体の統一性を保つことが重要とされています。
【公用文書別】「等」「など」の使い分け参考例
公用文の種類によって「等」「など」の使い分けには違いがある場合があります。実際の使用例を参考に、適切な判断の参考にしてください。
法令・条例での参考例
法令や条例では、「等」の使用が一般的です。
よく見られる使用例:
- 「申請書等の必要書類を提出すること」
- 「市民税等の納税証明書」
- 「建築基準法等の関係法令に基づき」
背景: 法的効力を持つ文書では、明確な表現が求められる傾向があるため
通達・通知文での参考例
官公庁から発出される通達や通知文でも「等」が多く使われています。
使用例:
- 「関係書類等をご準備ください」
- 「申請手続等についてお知らせします」
- 「税務署等にお問い合わせください」
注意点: 通知を受ける相手が一般市民の場合、理解しやすさを考慮した表現も検討される場合があります。
申請書・届出書での参考例
市民が記入する申請書や届出書では、記入者の理解しやすさも考慮される場合があります。
一般的な例:
- 「必要書類等をご用意ください」
- 「印鑑等をお持ちください」
場合によっては:
- 説明欄での補足説明
- 記入例での分かりやすい表現
議事録・報告書での参考例
公的機関の議事録や報告書では、記録の正確性が重要視されます。
議事録での一般的な考え方:
- 発言内容をそのまま記録する場合は、発言者の表現に従う
- 要約や整理する場合は「等」を使用することが多い
報告書での一般的な考え方:
- 客観的な事実報告では「等」を使用することが多い
- 「売上実績等について報告いたします」
公用文作成指針を参考にした使い方
公用文での「等」「など」使い分けは、各種指針やマニュアルを参考に行われることが一般的です。主要な指針を確認し、実務での参考にしてください。
文化庁「公用文作成の要領」での記載内容
文化庁が定める「公用文作成の要領」は、公用文作成の基本指針として参考にされています。
主な記載内容:
- 例示表現には「等」を使用することについて言及
- ひらがな表記よりも漢字表記を基本とする考え方
- 文書の統一性を保つための一貫した表記の重要性
参考となる表記例:
- 推奨例「関係書類等」
- 注意を要する例「関係書類など」
※詳細は文化庁公式サイトをご確認ください
各省庁の文書作成マニュアルでの傾向
各省庁でも独自の文書作成マニュアルを策定していますが、多くで「等」の使用が標準とされています。
一般的な傾向:
- 行政文書では「等」を使用
- 国民向け広報資料では理解しやすさも考慮
- 法令関係文書では「等」の使用を基本とする
- 予算書、決算書等の数値を扱う文書では「等」を使用
自治体の公文書作成ルールの傾向
地方自治体でも、国の指針に準拠した公文書作成ルールを策定している場合が多くあります。
一般的な自治体での傾向:
- 条例、規則では「等」を使用
- 住民向け文書では理解しやすさも考慮
- 庁内統一を図るため、部署間での表記統一
実務での参考となる判断要素:
- 文書の公式性の程度
- 読み手の属性(職員向けか市民向けか)
- 文書の目的(規制的内容か案内的内容か)
よくある事例と改善の参考案
公用文作成の現場でよく見られる「等」「など」の事例と、改善の参考案を紹介します。実務での品質向上の参考にしてください。
「など」を使用している事例
事例1: 条例文での使用
現状: 「建築許可申請書などの必要書類を提出すること」
参考改善案: 「建築許可申請書等の必要書類を提出すること」
事例2: 通達文での使用
現状: 「関係部署などと連携を図ること」
参考改善案: 「関係部署等と連携を図ること」
事例3: 予算書での使用
現状: 「人件費などの経常経費について」
参考改善案: 「人件費等の経常経費について」
「等」の使用参考例
分野別参考例:
法務関係:
- 「契約書等の法的文書」
- 「民法等の関係法令」
- 「裁判所等への提出書類」
財務関係:
- 「予算書等の財務諸表」
- 「税務署等への申告書類」
- 「監査法人等による確認」
総務関係:
- 「人事異動等について」
- 「会議室等の利用について」
- 「出張等の手続きについて」
判断に迷う場合の参考要素
公用文作成で判断に迷う場合の参考要素を整理します。
参考要素1: 文書の公式性
- 高い公式性 → 「等」の使用が一般的
- 中程度の公式性 → 基本的に「等」、説明部分では「など」も
- 低い公式性 → 読み手に応じた選択
参考要素2: 読み手の属性
- 職員・専門家向け → 「等」の使用が一般的
- 一般市民向け → 「等」を基本として、理解しやすさも考慮
- 特定の配慮が必要な読み手 → 場合によって「など」も検討
参考要素3: 文章の性質
- 規制的内容 → 「等」の使用が一般的
- 案内・説明的内容 → 「等」を基本として、親しみやすさも考慮
- 事務連絡 → 「等」での統一が一般的
公用文以外との使い分け比較
公用文での「等」「など」使い分けをより深く理解するため、他の文書種別との比較を通じて、その特徴を確認しましょう。
ビジネス文書との違い
公用文の特徴:
- 「等」の使用がより重視される傾向
- 文書の権威性と客観性を重視
- 統一性への要求が高い
ビジネス文書の特徴:
- 相手との関係性によって「等」「など」を使い分け
- 親しみやすさも考慮される場合がある
- 業界慣習の影響もある
参考例比較:
公用文: 「申請書等をご提出ください」
ビジネス文書: 「資料等をお送りいたします」または「資料などをお送りします」
学術論文との違い
共通点:
- 客観性と正確性を重視
- 「等」の使用が基本的
- 引用での「田中等(2023)」表記
相違点:
- 学術論文では読み手の専門性がより高い場合が多い
- 公用文では法的効力も考慮される場合がある
- 公用文では国民への説明責任も重要な要素
一般文書との違い
公用文の特徴:
- 表現の制約がある場合が多い
- 統一ルールの遵守が重要視される
- 誤解を招く表現は避ける傾向が強い
一般文書の特徴:
- 文章の目的に応じた自由な表現が可能
- 読み手との関係性を重視した選択ができる
- 創意工夫による表現の工夫が可能
【FAQ】公用文での「等」「など」使い分け参考情報
公用文作成の現場でよく寄せられる質問への参考情報をまとめました。実務での判断の参考にしてください。
Q1: 条例作成時の参考ポイントは?
A1: 条例では「等」の使用が一般的です。
条例は法的効力を持つ文書のため、表現の統一性が重要視されます。多くの自治体で「建築基準法等の関係法令」「申請書等の必要書類」のように、「等」を使用しています。
参考となるポイント:
- 一つの条例内で表記を統一する
- 他の自治体の条例も参考にする
- 法務担当者との事前確認
注意: 具体的な条例作成については、必ず法務担当者や上司にご相談ください。
Q2: 住民向け文書での参考ポイントは?
A2: 基本は「等」ですが、理解しやすさも考慮される場合があります。
住民向けの広報文書や申請書の説明文では、以下のような使い分けが参考になります:
「等」がよく使われる場面:
- 正式な手続きの説明
- 法令名や制度名の列挙
- 公的な用語の説明
「など」も使われる場面:
- 具体例の説明
- 日常的な表現での補足
- 理解しやすさを重視する説明
参考例:
正式: 「住民票等の証明書が必要です」
説明: 「準備するものは筆記用具やはんこなどです」
Q3: 議会資料での参考ポイントは?
A3: 議会資料では「等」の使用が一般的です。
議会に提出する資料は公文書として正式性が要求される場合が多いため、「等」での統一が一般的です。
議会資料での一般的な傾向:
- 提案理由書では「等」を使用
- 資料の説明文でも「等」で統一
- 議員への配布資料も同様
例外的なケース:
- 議員との非公式な質疑応答資料
- 住民説明会用の補助資料
Q4: メールでの参考ポイントは?
A4: 公務でのメールも「等」が基本的に使われています。
庁内メール、他機関とのメール交換では「等」を使用することで、公務の性質を保つことができます。
参考例:
庁内連絡: 「会議資料等をご確認ください」
市民対応: 「必要書類等についてお問い合わせいただき」
業者対応: 「仕様書等をお送りいたします」
Q5: 過去の文書と表記が違う場合の参考ポイントは?
A5: 現在の指針に合わせることが一般的です。
過去の文書で「など」が使われていても、現在作成する文書では所属機関の現行ルールに従うことが重要です。
参考となる対応方法:
- 新規作成文書では現行ルールを適用
- 改正時には表記も更新を検討
- 庁内での統一方針を確認
Q6: 他の自治体で「など」を使っている場合の参考ポイントは?
A6: 自団体の方針に従うことが基本です。
他自治体の表記に関わらず、自分の所属する自治体の公文書作成ルールに従うことが重要です。
判断の参考となる優先順位:
- 自治体の公文書作成要領
- 国の指針(文化庁等)
- 他自治体の事例
- 業界での一般的な慣習
まとめ:適切な使い分けの参考ポイント
公用文での「等」「など」使い分けは、文書の統一性と読みやすさを保つ重要な要素です。この記事で解説した内容を参考に、実務での活用ポイントをまとめます。
使い分けの参考となる基本的な考え方
公用文では「等」が基本的:
- 法令、条例、通達、報告書では「等」がよく使用される
- 文書の格式性と客観性を保つ効果
- 文化庁の指針でも参考となる表記
場合によって「など」も使用される:
- 住民向けの分かりやすい説明
- 日常的な表現での補足説明
- 親しみやすさを重視する場面
実務での参考チェックポイント
公用文作成時には以下の点を参考にしてください:
□ 文書の種類確認
- 法令・条例 → 「等」が一般的
- 通達・通知 → 「等」が基本的
- 申請書・届出書 → 「等」が推奨される傾向
- 説明資料 → 状況に応じて判断
□ 読み手の確認
- 職員・専門家向け → 「等」が一般的
- 一般市民向け → 「等」基本、理解しやすさも考慮
- 特別な配慮が必要 → 場合により「など」も検討
□ 統一性の確認
- 一つの文書内で表記統一
- 関連文書との整合性確認
- 過去の文書からの改善点確認
品質向上のための参考ポイント
継続的な学習:
- 文化庁の最新指針を確認
- 他自治体の優良事例を参考
- 庁内研修での知識更新
組織的な取り組み:
- 部署内での表記統一
- チェック体制の整備
- マニュアルの定期更新
適切な「等」「など」の使い分けを心がけることで、公用文の品質向上と行政サービスの向上に貢献できます。日々の文書作成において、この参考情報を活用し、質の高い公用文作成を目指しましょう。
参考資料・リンク
免責事項 本記事の内容は参考情報であり、法的アドバイスや公式指導ではありません。実際の公用文作成においては、必ず所属機関の規定や法務担当者の指導に従ってください。本記事の内容により生じた損害について、執筆者・監修者は責任を負いません。
最終更新: 2025年7月1日